三国志から中国史好きになった私ですが、中国の歴史小説好きが最初に読む作品は大概決まっています。
「三国志演義」「史記」「水滸伝」ではないでしょうか。これらを元ネタにして、多くの歴史小説が書かれています。
三国志は有名ですよね。史記は、古代中国の成り立ちから、前漢の武帝時代までの歴史書です。マンガ「キングダム」の内容も元ネタは史記から来ています。
水滸伝は北宋から南宋にかけての話ですが、民間伝承の集まりみたいな話で荒唐無稽な物語です。
北方謙三版水滸伝
水滸伝って民間伝承の集まりだけあって、話が荒唐無稽なんですよね。
大筋は、北宋末期を舞台に腐敗した政治に立ち向かう108人の英雄が、梁山泊に集結して戦うみたいな物語なんですが、一つのエピソードが終了したら、ほぼその人は終了みたいな感じで、物語に連続性がないんですよね。しかも対して光を当てられない人もいます。
水滸伝の再構築
内容としては面白そうなんですが、物語の連続性もなく、各キャラクターも今一定まっていない、こんな物語を再構築したのが「北方謙三」先生です。
なぜ読み始めたのかは覚えていないんですが、最初読んだ時は、衝撃を覚えました。めちゃくちゃ面白いんです。
登場人物一人一人を再構築したことによって、各キャラクターが魅力的になっています。そこに架空の青連寺という組織を敵役として設定し、闇の塩の道というスパイスを加えることによって、極上のエンターテイメントに仕上がっています。
魅力的な登場人物の生き様と死に様
元ネタの水滸伝では108の星が梁山泊に集合するまでは、基本的に死にません。(集合した後は、あっさりと死んでいくんですが)しかし、北方版の水滸伝で衝撃を受けたのが、主要人物が死んでいくんです。
魅力的に描かれて、ここから活躍するんだろうなと思っていたら、死んでいきます。代表的なのは青面獣楊志の死ではないでしょうか。序盤で活躍して、ここから大きく飛躍しそうな感じで書かれていた楊志が死んでしまいます。ここは本当に衝撃的でした。でも死に様も生き様も恰好いいんですよね。ここでは説明しずらいので、ぜひ皆さんに読んで頂きたいです。
この楊志の死が、後の「楊令伝」「岳飛伝」「チンギス紀」への布石となっていきます。
意外な人物の使い方
史進という禁軍師範だった人物がいるんですが、元ネタではこの人物は九紋龍史進を登場せせる舞台装置の一つにすぎません。しかし北方水滸伝では、ずっと王進が登場します。悩んだり、行き詰ったり、成長しきれない人物が、王進のもとに送り込まれては再生していきます。
また童貫という禁軍の将軍が登場するのですが、元ネタではほとんど意味のないキャラだったのに、北方水滸伝では、たちはだかる強力なライバルとして終盤を盛り上げてくれます。
それ以外でも光が当たらなかった、主要ではない方の108の英雄たちのモブがいる訳ですが、ここも全員キャラ立ちさせて、皆が強烈な生き様を見せてくれます。
見返してみて
だいぶ前に読んだきりで大筋では覚えていても忘れている部分が結構多くて、今読み直していいます。
また詳しい感想など語っていけたらいいなと思っています。


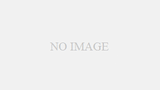
コメント