来年の大河ドラマの主人公は「羽柴秀長」に決まりました。
かの有名な太閤、「豊臣秀吉」の弟になります。私の好きな武将の一人です。地味な印象なのですが、豊臣政権が崩壊してしまったのは、結局この人が先に亡くなってしまったからだと思います。
徳川政権の成立に多大な功績があった藤堂高虎も、もともとこの人の配下でしたしね。
毛利隆元
さらっと羽柴秀長に触れましたが、私の好きな武将、栄えある一人目は毛利隆元です。
私は山口県出身なので、やはり毛利家びいきになります。毛利家と言えば有名なのは「毛利元就」。大河ドラマの主人公にも選ばれました。当時の中村橋之助(現中村芝翫)が演じていました。
安芸の国(現広島県)の一介の国人領主から、一代で中国地方一帯を支配する戦国大名にのし上がりました。領土の膨張率でいえば戦国時代でも屈指の人になります。
この人の長男が毛利隆元です。
優秀な弟たちに比べて
毛利元就の次に有名なのは、「吉川元春」に「小早川隆景」です。小早川隆景は豊臣秀吉とも縁が深いので、来年の大河ドラマでも絡んでくるかもしれませんね。
毛利隆元 人質時代
毛利隆元ですが、当時大勢力だった大内家に毛利家が従属した関係で、幼少期は山口に人質として出されていました。人質とはいえ、成長すれば大内家を支える重要な武将になるわけですから、きちんとした待遇を受けていたようです。
当時の山口は今と違って、当時の最先端を走っていました。大内家は日本でも有数の守護大名家であり、日明貿易など中国とも交易を行っていました。また応仁の乱以後、京都の治安が急激に悪化したしたため、ここから逃れた貴族階級などが山口に亡命、非常に文化的にも高度な状況でした。
そうした中で育った隆元ですから、当時最先端の教育を受けていたんでしょうね。
優秀に育つ弟たち
さて、隆元はこういう状況でしたが、毛利家自体は大内家の従属国衆とはいえ非常にちいさな存在でした。毛利家の北方には尼子家が大きな勢力としてありました。また安芸の国は尼子勢力と大内勢力がひしめき合っていました。
この状況打破のための元就の策略が次々とはまっていきます。まず長女を、北方の宍戸家に嫁がせて毛利領の北方にあった宍戸家と一門になります。次に瀬戸内海近くに勢力のあった小早川家の混乱に乗じて、三男の隆景を養子に出します。小早川隆景の誕生です。
さらに、元就のお嫁さんの実家の吉川家にも混乱に乗じて次男の元春を養子に出します。吉川元春の誕生です。
小早川家は瀬戸内海に面した領土を持っており水軍衆を抱えていました。また吉川家は勇猛で有名な家系でした。そうした背景もあってか、小早川隆景は有能な智将として、吉川元春は勇猛な武将して成長していきます。
戦乱絶えない安芸の国で揉まれたこと。養子に行って苦労もあったと思います。弟たちは優秀な武将として元就を支えていくことになります。
三本の矢
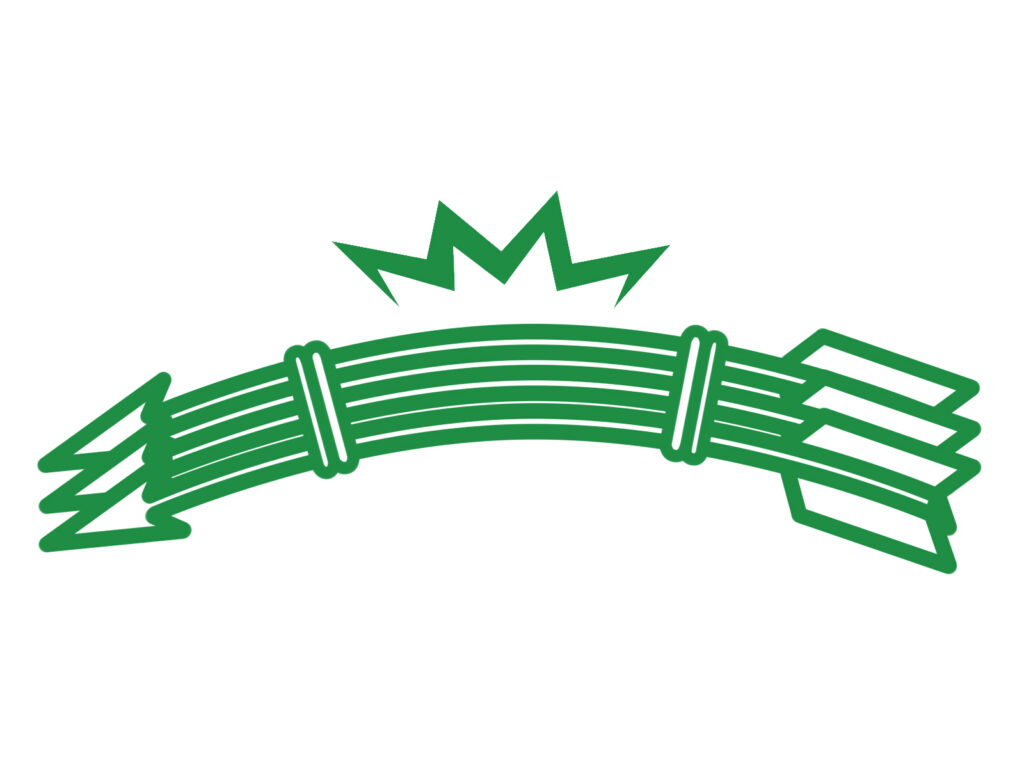
まあこういう状況下で隆元は山口から帰還して、元就の後継者として育って行くことになります。戦争まっただ中の安芸と高度な文化と平穏な山口で育った環境の違いからでしょうか、どうも兄弟仲はしっくりいっていなかったようです。
有名な「三本の矢」という逸話があります。元就の臨終の際に、三人の兄弟を呼び、一本の矢は簡単に折れるが、三本の矢は折れない、だから兄弟結束して頑張りなさいというお話です。実際には隆元は元就よりかなり早く亡くなっているので逸話時代は嘘になります。
元ネタは「三子教訓状」という元就が残した手紙になります。元就は非常に筆まめで、しかも手紙が異常に長い傾向にありました。この手紙にも兄弟仲良くとクドクド一杯書かれています。
しかし、これで兄弟仲が好転したというお話は残っていないようです。
ちなみに、この三子教訓状が出された背景ですが、隆元の性格も大きいと思います。とにかくネガティブで自己評価が異常に低い。家督を元就から譲られた際には、きちんと後見してくれないなら、孫の輝元に家督を譲るとごねています。また、自分が継いだら毛利家はおしまいだなんだと愚痴を言っている書物も残っています。
厳島の戦い
そんな隆元ですが、強気になったこともあります。それが「陶晴賢」との決戦です。
月山富田城攻めの失敗のあと、大内家の勢威に陰りが見え始め、結局お家騒動の結果、陶晴賢が謀反を成功。大内義隆は自害。大友家からの養子を入れて大内家は続きますが、陶晴賢が実質当主のような状態になります。
元就も表向きは陶晴賢に協力して、その間に安芸の国をほぼ手中に入れるなど、どさくさ紛れに勢力を拡大していました。とはいえ、まだまだ毛利家と陶家では全然規模が違っていました。幼少期に山口で育ち、大内義隆に可愛がってもらったことも影響したのかもしれません。隆元が陶との手切れを進言します。家臣たちへの根回しも行ったようです。元就も陶との手切れを決断します。
そして前哨戦を経て、厳島にて見事に陶の大軍を毛利家が打ち破ります。有名な「厳島の戦い」です。
毛利隆元の死
厳島の戦いの後、周防、長門(現山口県)へ侵攻した毛利軍は苦戦しながらも見事に周防、長門の制圧に成功しています。隆元も活躍しています。(資料は乏しいんですが)その後、領土を接した大友家と北九州から博多の支配をめぐって争うようになっていきます。尼子家とも石見銀山制圧をめぐって争いを繰り返しています。
大友家とは和睦に成功して、尼子家をつぶそうとなった矢先、隆元が亡くなるという大事件が起こります。毒殺とも食中毒ともいわれています。相当元就も嘆き悲しんだでしょうね。この時の接待役やお付きの武将が処刑されています。
こうして大した活躍も描かれないまま隆元は退場してしまいます。残ったのはネガティブエピソードや情けない逸話が多かったこと、その後も弟たちが大活躍したこと、高齢の元就が尼子家滅亡まできっちり終わらせて大往生したこともあって、隆元の評価は芳しくありません。
最近の評価
歴史が面白いのは時代がたつと研究が進んで評価が変わることです。有名なところですと、北条早雲が一介の素浪人から戦国大名にのし上がった話。今では室町幕府内のれっきとした武士だったことがわかっています。また斎藤道三の国盗り物語は親子二代の物語。今川義元は公家風の軟弱武将ではなかったなどあります。
毛利隆元はマイナーな武将なので、研究が進むのはなかなか望めないかもしれません。しかし隆元の死によって、毛利家がぐらついたのは確かです。山口で最先端で育ったことにより、経済感覚が鋭かったのか、荒波にもまれず育ったのが良かったのか、商人からの信頼は高かったようです。隆元の死後、元就の名前ではお金が借りられず、(元就の謀将ですから特に信頼ありませんでした)、毛利家の財政が急激に悪化したようです。石見銀山を手に入れるまでは、お金に以後かなり苦労したようです。
また隆元のこなしていた仕事が元就、元春、隆景にも回ってくるようになったそうですが、隆景はこんなに色々としていたのかと驚いたようです。多分縁の下の力持ちのような感じで、派手に活躍する元就、元春、隆景を支えていたんでしょうね。
早世してしまったことで隆元の功績の部分が元就に吸収されてしまった側面もあるんではないでしょうか。しかし、亡くなってから大きな存在だということが、皆に知られて良かったのかもしれません。元就没後も、毛利輝元(隆元の息子)を小早川隆景、吉川元春がしっかりと支えていきました。但し、輝元は叔父2人からきつく教育されたようで、早く死んだ父親を恨んでいたかもしれませんが。
いつか正当な評価を
最近はゲームの「信長の野望」でもかなり高い評価になっている毛利隆元。ゲームの数字だけでなく、実際の資料的な評価も上がることを望んでいます。
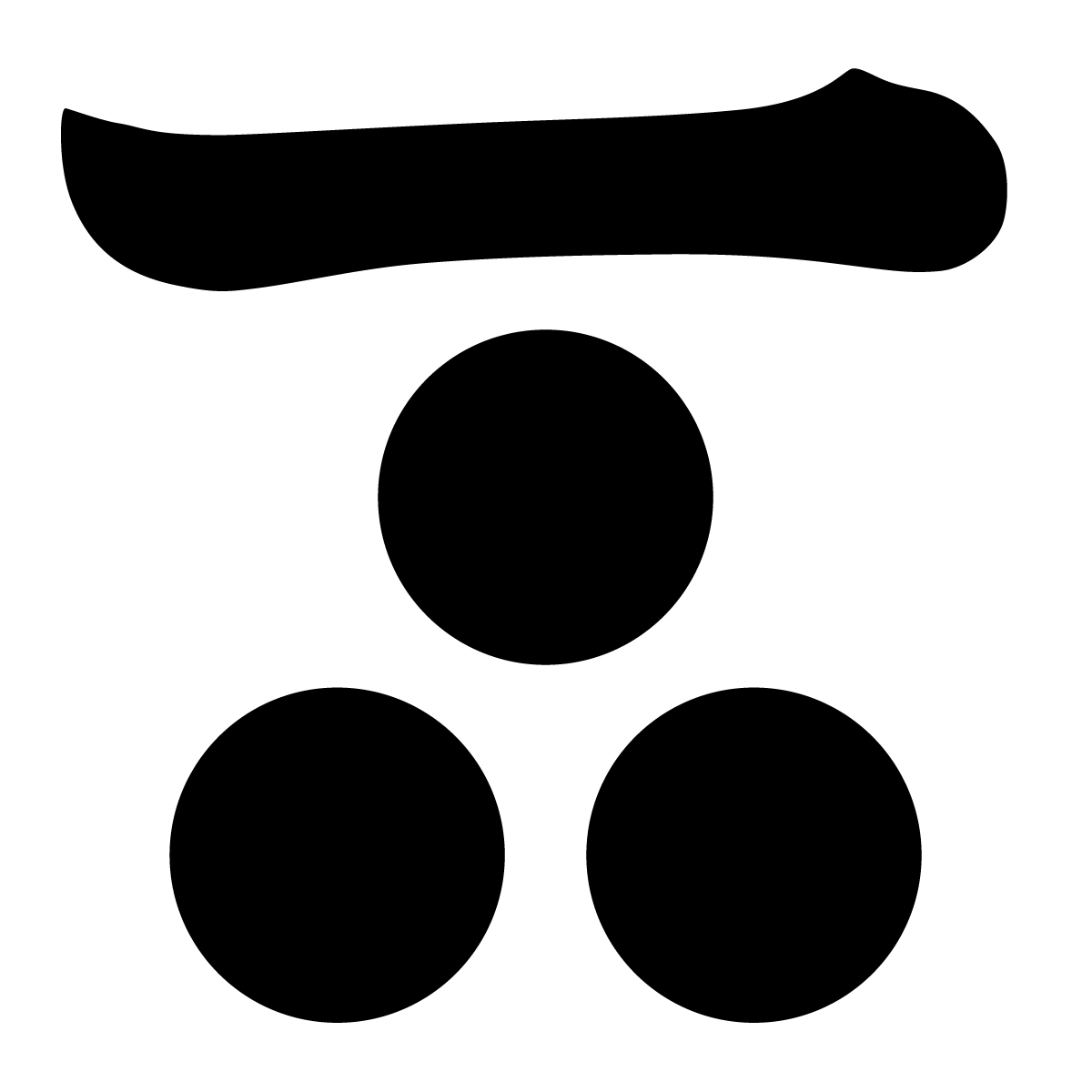

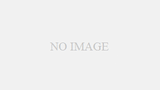
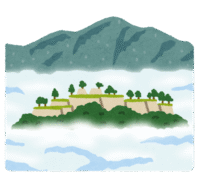
コメント