武士が統治の前面にでてきた鎌倉時代以降、政治力の高い武士は多く出てきました。最初期でいうと北条泰時、御成敗式目の制定など、武士が政治を行っていく上で重要な指針を制定したのは大きな功績になります。(代々の執権は比較的優秀な人が多く、鎌倉幕府の安定は執権北条氏の力が大きかったと思います。)
室町時代でいうと、足利直義、足利義満、その後は徳川家康といったところの政治力が光ります。但しこれらの人には多くのブレーンが存在したうえに、先人の真似ができるといった利点がありました。
それを考えると源頼朝の政治力は異常です。先人の平清盛は、藤原氏などの政治手法を継承して、一族に官職を与えて殿上人を占める、天皇の外戚になるなどの手法を用いています。平氏は全盛期を迎えましたが、平清盛の手法は、当時の武士階級の望む政治手段ではなかったため、最終的には衰退の憂き目にあいます。
源義経との関係から人気の無い源頼朝ですが、その政治手腕の高さには脱帽します。
源頼朝
当時の最先端と言えば、言わずもがなで京都になります。京都の都で行われていることが教育の最先端であり、教養の最先端であり、流行の最先端でした。源頼朝も源義朝の嫡男であり、順調に成長すれば河内源氏の棟梁として、そこそこの官位を得て、そこそこの地位を得るはずでした。しかし、そうはなりませんでした。
伊豆への流罪
平治の乱の敗戦によって、源義朝は戦死、さらに多くの源氏が討ち取られる事態になります。頼朝も平氏に捕らえられますが、平清盛の奥方の命乞いによって、死ぬことは免れて伊豆へ流罪になります。ここで京都から追い出されることになるわけですが、これが頼朝にとってはいい経験になったのではないでしょうか。
幼い時分に京都で当時の最先端の文化、政治に触れ、さらに父義朝、平清盛の政治闘争を見たことによって、今の時代の流れを知ることができました
その後伊豆に流され、現地の武士階級の実際の生活を知り、平家の政治に対する不満を肌で感じることができたのは大きな経験になったのではないでしょうか。
挙兵
その後、平氏追討を旗印に挙兵することになります。実際には当時の平氏の政治に対する不満があった関東の武士階級から神輿に担がれただけだったとは思います。源平の争いと言われていますが、実際には頼朝旗下に平氏の流れをくむ一族が多く参加しており、単純に当時の武士階級の要望を通すために、源頼朝は血脈的に都合が良かっただけではないでしょうか。
しかし、只の神輿にならなかったのが頼朝の凄さです。この戦いのさなか、滅ぼした一族の土地を取り上げ、新たに土地を上げるといったことを行い「御恩と奉公」という鎌倉幕府の支配の原点になる部分を実践しています。
優秀なブレーン
また勇猛な坂東武者を従えて戦いを任せる一方で、頼朝が凄いのは文官(政務)を行える人材を京都から呼び寄せています。大江広元、三善康信、中原親義などが有名です。下級貴族ですが有能な彼らを遣うことによって、幕府の政治体制を作っていきます。大江広元は政所の別当に、三善康信は問注所の執事になっています。特に問注所は訴訟事務を取り扱う部署になりますので非常に重要な役職でした。(土地関係の訴訟をおろそかにすることが、最も武士階級の利害に直接影響を与えます。)
全国への守護、地頭の設置も大江広元の献策と言われており、全国への武士階級の支配の拡大の大きな要因となっています。
朝廷対策
当時は後白河法皇が院政を敷いており、日本第一の大天狗と称されていました。保元の乱、平治の乱、その後の治承寿永の乱でも、双方の間をうまいこと渡り歩きながら、政治的に生き残ってきた人物です。この人物とも対等に渡りあい、源義経との闘争においては、うまいこと逆利用して先述の守護・地頭の全国への設置を認めさせtいます。
鎌倉から動かず、京都政局から距離を置きながら、一方で京都政局を動かすその手腕は特筆ものではないでしょうか。今のように京都と鎌倉がすぐ行き来できる時代でないことを考えると驚異的と言えます。
奥州藤原氏滅亡と頼朝の死
源義経をうまく利用することで、目の上のたんこぶだった奥州藤原氏の滅亡も実現させます。ここら辺の手腕は優れているものの、兄弟との関係から陰湿ともとらえられ。頼朝の不人気の要因にもなっていると思います。但し、義経と頼朝の関係性でいうと、義経の振る舞いには大いに問題があったといえます。頼朝は神輿であり、旗下の武士階級の要望を満たせなければ、自身の命が危ない状況にありました。実際には綱渡りのような状態で生き残ってきたといえます。しかし、義経にはそうした兄頼朝の状況に対する洞察はなかったように思えます。戦術の天才ではありますが、政治には疎かったんでしょうね。
絶頂期を迎えた頼朝ですが、あっけなく死亡してしまいます。そして、息子の頼家、実朝も不慮の死を遂げ、血脈は絶えてしまいます。その後鎌倉幕府は執権北条氏を中心に合議制でうまく運営されていきますので、後期まではうまくいきます。(後期になると北条氏による専制が強くなっていくため)
源頼朝が生きていたら、鎌倉幕府はどのような完成形を描いていたのか、興味ふかいところです。

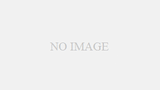
コメント