ゲームの信長の野望をプレイする場合、初心者がプレイしやすいのはやはり織田信長です。
実際に天下統一目前でしたし、その後を継いだ豊臣秀吉が天下統一しているので、当然ですよね。
次にプレイしやすいのは「武田信玄」ではないでしょうか。(島津家という意見もあるかもしれませんが、あれはゲームの特性上、敵が背後に存在しないという特殊条件なので排除します)なんといっても家臣の優秀さと多さは群を抜いていますし、当主の総合能力もゲーム随一ですからね。
しかし私は武田信玄は過大評価が過ぎると思っています。
武田信玄
甲斐(現山梨県)の戦国大名で、源義家の弟、源義光の血を引く名門一族生まれです。
父親を追放して当主になると、その後信濃(現長野県)に進出します。近隣の今川義元、北条氏康と三国同盟を結んだ信玄は順調に信濃の制圧をすすめていきます。この時、上杉謙信と領土を接することになり、その後川中島で何度も戦ったことは有名です。
また同時に上野(現群馬県)の西部にも進出して、西上野の領有化も行っています。
さらに今川義元が桶狭間の戦いの戦いで敗れ死亡した後は、三国同盟を破棄して、混乱した駿河(現静岡県)へ侵攻して、駿河の領有化も実現しています。
内政でも信玄堤など治水政策を行い、金山開発によって領国を潤し、様々な人材活用を行って、武田四天王をはじめ、多くの優秀な家臣を従えていたことでも知られています。
そして満を持して、京都に上洛に向かい、徳川家康を三方ヶ原の戦いで破った後、無念にも病で生涯を閉じることになります。
これが一般的な武田信玄のイメージです。
過大評価の原因
過大評価の原因として、徳川家康が大きく関係しています。この三方ヶ原の戦いでの敗戦もそうですし、徳川家康は終始武田信玄とは領土を接して鎬を削っていました。ご存知の通り、戦国時代を最後に勝ち上がったのは徳川家康です。徳川幕府初代将軍徳川家康は優秀でなければいけないんです。ですので、家康を破った武田信玄もまた優秀である必要があったわけです。
また、織田信長が武田家を滅亡させた後、徳川家康は旧武田家臣を匿っていました。織田信長が本能寺の変で亡くなっていなければ、そのまま日陰の身として生きるしかなかった人たちです。しかし、信長が死亡して、甲斐、信濃は大混乱に陥ります。天正壬午の乱です。ここで旧武田家臣が家康方として活躍します。ここに家康は三河、遠江、駿河、甲斐、信濃を領有する大大名となります。
また家康配下の古くからの家臣であった、石川数正が豊臣秀吉方へ出奔するといった事件も起こりました。そこで三河流の兵制から甲州流の兵制に移行したという話もあります。
とにかく旧武田家臣が徳川家の中では大きな存在だったわけです。そんな人たちが武田信玄はすごかったと吹聴する、資料を書き残す、そうするとやはり武田信玄は偉大だったと後世にはいい継がれることになります。
なぜ過大評価なのか
信濃侵攻
では実際になぜ過大評価なのかですが、結構行き当たりばったりなんですよね。
戦略の天才と言われる武田信玄ですが、基本的には近視眼に領土拡大しているだけなんですよね。確かに今のようにグーグルマップがあるわけではないですから、どこが平野部かなんて大局的には見れません。(平野が多いと、農業生産力が上がって人口もおおくなります)しかし、古代からの記録で、豊かな土地はわかっていたわけです。信玄の立地から言えば、基本的に豊かなのは武蔵(現東京都方面)方面なわけですから、こちらに侵攻すべきだったんですよね。
しかしこちらには北条家があり(北条早雲、北条氏綱の2代を経て急成長していました)、海に面した駿河には今川家(こちらは室町幕府内の名門守護)があったため、弱小勢力ひしめく信濃に進出していきます。
しかし、信濃制圧も簡単にいったわけではなく村上義清に手痛い敗戦を喫するなどして、かなりの年月を要しています。しかも信濃というのは、今の長野県の地図を見てもわかる通り、各地に盆地が点在しており、それ以外は山と、交通の連絡が悪く、農業生産力も高くないといった有様でした。だからここを領有したといってもそこまで国力的には上がらなかったわけです。
川中島の戦い
信玄を語るうえで、上杉謙信とのライバル関係は欠かせません。上杉謙信の本拠地。春日山城と川中島の地は非常に近く、ここを抑えられると上杉謙信にとっても嫌なわけです。信玄にとってみれば、ここから越後に出れば、海に出られるわけで、経済的にはおいしかったはずです。
しかし、武田信玄に海に出て越後を領有化する意図があったかというと多分なかったのではないでしょうか。そこまで大きな戦略意図を持てない人だったと思うんですよね。
確かに上杉謙信は無類の戦上手で、これに勝てる大名ってほぼいなかったとは思います。だからこそ、何回ここで無駄な戦しているんだろうと、思うわけですよね。三国同盟があるうちに、集中して上杉謙信を倒す、できないなら和睦して戦わない、その戦力をほかに回した方が良かったと思うんですよね。
まあ上杉謙信の面倒くさい性格からしたら、そうした周囲の常識が通用しなかった可能性もありますが。。。
川中島で何回無駄に衝突してんだよって話ですよね。これ織田信長なら絶対しないですよね。
駿河侵攻
こちらが、私が武田信玄を過大評価という一番の理由なんですが、とにかく外交が下手すぎます。武田勝頼が武田家を滅亡させた当事者なので、悪く言われるわけですが、武田勝頼の代には、武田家の周辺大名と関係が非常によくないわけです。全ての原因は武田信玄にあります。
今川義元が亡くなった後、今川氏真ではうまく統治ができず、国人領主の離反が始まります。三河では徳川家康が独立し、織田信長と同盟を結びます。ここで、三国同盟を見限った武田信玄は今川領の駿河に侵攻します。北条家は三国同盟を破棄しなかったため、ここに北条家と武田家の同盟も終了します。
信玄と家康は密約を結んで、2方向から今川家に侵攻、ここに名門今川家は終焉します。(今川氏真は生き残って、江戸時代も御家自体は続いていきますが)しかし、この侵攻のさなか、小競り合いが起こって武田家と徳川家もギクシャクしていきます。
駿河、信濃、甲斐と領国を拡大した信玄ですが、北の上杉謙信、東の北条氏康、西の徳川家康とほとんどと険悪な関係になります。織田信長のだけは友好な同盟関係を結んでいましたが、德川領に突如侵攻したことによって、織田信長との同盟もなくなりました。この時、信長は相当怒ったらしく、以後武田家は許さないと誓ったようです。これが後の武田勝頼の悲劇に繋がります。
行き当たりばったりで攻めやすいところに片っ端から侵攻して、周辺の大名には根回しをしない。戦術家としては非常に優秀なんでしょうが、戦略家としては疑問符がつきます。
北条家は三代目の北条氏康が死亡したのち、四代目の北条氏政と同盟関係が復活していますが、周囲全て敵で、北条家とだけ結んでいてもって感じですよね。
跡継ぎ問題
これも非常に大きいと思うんですよね。例えば北条家では、当主はある時点で後退して、後見しながら徐々に権力移譲するスタイルでした。これは毛利家もそうですし、織田信長も織田家当主の座は息子に譲っています。しかし、信玄は後継者の義信を自害に追い込んだ後、確固とした跡継ぎを決めていませんでした。
武田勝頼は最初、諏訪家の養子に出されていましたが、義信の自害に伴って武田家へ戻されました。しかし非常に不安定な地位で、正当な後継者は勝頼の子(信玄から言えば孫)だとされていたようです。勝頼はそれまでの繋ぎの名目上の当主といった感じでしょうか。
こういう不安定な立場に勝頼を置いてしまったことで、信玄譜代の家臣と勝頼の間でもめ事が相当あったことは想像に難くありません。
武田家滅亡は武田信玄のせい
領土を拡張しても、このような状況で武田家を引き継がせられたら、遺った者もたまらないのではないでしょうか。
武田家が最終的に滅亡したのも武田信玄のせいだと思うんですよね。今川氏真も今川家を遺したという意味ではある意味偉大です。根絶やし文化は日本にはあまりないので、小さな大名として生き残る目を摘んでしまったのは武田信玄の生き様が影響しているのではないでしょうか。
優秀な戦国大名ではありますが、戦国最強という評価はやはり過大評価だと思います。

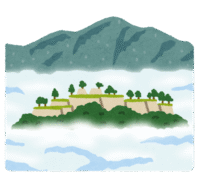

コメント